仮説設計と課題検証の根本から
── 「パークナードテラス南荻窪 景邸」を手がけるにあたり、お二人の立場と役割について教えてください。
山枡: 私は当社で二つの部門を担当しています。一つはまちづくり技術部の主幹で、仕入れをした土地を開発設計し、設計、施工監理を行うのが仕事です。もう一つが東日本分譲開発支社 建築技術部 分譲設計センターの所長で、宅地にした後に戸建建売分譲を販売するにあたり、建物の設計、インテリア、実施設計という業務があり、それらを統括しています。家、街並みというハードをつくるために、どのようなデザインコードにして、ルールやガイドラインを設けることによって、周辺にどういう影響をもたらすのか、住んだ方や新しくできた街が既存の街にどう馴染んでいくかを検討します。

山枡正幸さん(東日本分譲開発支社 建築技術部 分譲設計センター 所長、兼 街づくり技術部 東部街づくり技術課 主幹)
近藤: 現在は部署変更がありましたが、本プロジェクトの企画段階においては営業の責任者として事業に取り組んでおりました。仕入れた土地に対してどのように商品設計をするのか、マーケット調査からターゲット、価格、プロモーションなどを検討します。広告代理店さんと協力し、どれだけ集客してどう販売していくか、マーケティングからHPへのアウトプット、販売〜お引渡しまでを行っております。
── plan-Aと出会ったのはどのような経緯だったのですか?
山枡: 最初は営業サイドから外部の会社と一緒にプロジェクトを進めようと打診がありました。「パークナードテラス南荻窪 景邸」に取り組むにあたって、販売価格の単価は当社が今までやってきた物件よりも高額帯になってくるため、丁寧に検討を進めたいというのと、アウトプットの質に関しても企画そのものから検討しなければなりませんでした。以前から弊社とお付き合いのある会社さんを数社、他部署から紹介を受けました。その中で今回のプロジェクトで我々が求めるものに一番近い存在であると考えたplan-Aさんにまずお声を掛けさせていただきました。
近藤: 外部デザイナー、コンサルティング会社など、さまざまな選択肢があった中で、アウトプットに直結するならplan-Aさんがいいと思いました。最初は率直に相澤さんに「今回の高価格帯物件にどうやって取り組んでいこうか迷っている」とご相談しました。打ち合わせが終わった段階で、相澤さんにお願いしようということが決まり、すぐに契約しました。2023年6月のことです。

近藤達弥さん(東日本分譲開発支社 分譲第一支店 第三営業所 所長)※1
相澤: 初めてお会いした日は、困っていることのふわっとした話でした。そもそも、パナソニック ホームズさんは、まちづくり、商品開発、企画力が、あまたあるハウスメーカーの中で群を抜いて優れています。このプロジェクトの前からもいろんな場面でご一緒していたので、それはよくわかります。今回の物件は、面開発してたくさんの物件を売れる値段で建て、どのような街並みデザインにするかという話とはそもそも尺度が違うもので、物件のつくり方の根本から入らないといけないと思いました。
具体的に言えば、高額帯の物件なので設備仕様を上げればいいという簡単な話ではない。その素地を整理する必要がある。極論を言えば、外観印象や街並みをどう見せるのかは、うちがやらなくてもご経験の中で進むと思いました。最初のその諸条件の仮説設計や課題整理、素地整理に注力するとよさそうだと思い、そこから始めました。
── plan-Aは仕事を受ける時に、まず徹底して現地を調査しますよね。
相澤: まず現地調査として、半径2kmを同心円上にひたすら歩くことをしました。その後に定量データのリサーチをやり、周辺の居住属性などを引き出し、それをもとに第二次の現調を行いました。感覚で見たものとデータで見たもののどれが正しいのか、それを比較検討していきました。
現調はいつも通り、道幅、動線、周辺交通量など、不動産事業者が最低限見ていることを現地で確認します。一方で、周辺居住者の生活感にかかわる観察もします。乗っている車の車種や自転車の停め方など、家族構成や年収、それに紐づく生活のレベル感、人生の志向性が垣間見られ、ペルソナ設計に直結します。それをひたすら地道に行います。
ここで大切なポイントは、plan-Aとしては定量データを提示するのですが、エンドユーザーのペルソナまでは提示しません。そもそもターゲットが誰なのか、という議論を我らが全て提示してしまうと、次にこのような物件を手がける時に会社にノウハウが残らなくなってしまいます。我々は、題材や素材はお渡しするし、問いも用意しますが、答えは出しません。会社と一緒に答え合わせをしていき、自らの仮説を一緒に作っていくという作業をします。

オリジナルの強弱検証プロセスで伴走
相澤: この物件に限らずですが、設計担当の方々が間取りを描いていくために、そもそもどういう人が住むのかというイメージが湧かないと描ききれません。本物件は敷地面積が限られて、延床面積も100平米程度になるだろうと見込まれており、ゆとりがあまりない状態でした。室内空間、庭、車庫……全てを充足することはできないので、何を優先するのか、どの程度どの配分でバランシングするのかのイメージが必要です。どのような方が住むのかのペルソナ設計ができれば、自ずと設計側も自走できるようになりますね。
── plan-Aが答えを用意せず、仮説を一緒に作っていく作業をしたということですが、具体的に用いた手段について教えてください。
相澤: オリジナルの強弱シートを用いました。物件の何が強くて弱いのかの強弱検証を行い、ターゲットの深掘りをしました。
山枡: 普段は設計に入るまで1〜2カ月くらいなのですが、今回は実際に手を動かすまで半年くらいかけました。今までは、キックオフと言って、最初に土地の周辺環境のハザードマップなど、客観的な資料を揃えます。そして、造成中に起きた、ご近隣との関係性などの事実をチームの全員に伝えて、営業は広告代理店の選定に入るという形で進みます。
今回は強弱シートを全員が一人ずつ、周りの意見を聞かずに、自分発で出していくということに取り組みました。すると、自分の思いと周りのギャップに気づくなかで、さらに全員の認識を一緒にしていくプロセスを踏みました。

── 相澤さんが答えを出すのではなく、まさにファシリテーションをしていったんですね。
相澤: ここで大切なのはプロセスです。強いところ弱いところを最終的に意識統一していくというよりは、関わる人それぞれでとらえる強み弱みが違うとわかることが大事だった。全員が一致することはどこかで歪みが出るものです。見ている人によって見るところが違うことがわかることが大事なのです。とは言いながらも、最終的にはその強弱シートもきちんと整ったものになり、個々で大きくぶれまくっていることがなかったのがパナソニック ホームズさんの強みではないでしょうか。我々は大きな矯正作業はしていません。
この強弱検証は、広告代理店が入った後の販売活動でも、代理店も含めて行います。その状態で一つのものをよく見せていくための露出合わせが難しいからです。
── ターゲットの深掘りはどのように行ったのですか?
相澤: ターゲットの深掘りは、最終的に4パターンのペルソナを作っています。目的確認を行い、予条件を整理して、その人たちが、定性的にどんな不安、不満、課題を持っていそうか。具体的に設計者のタスクに応じられるような作業に持っていきます。間取り、ランドプランで、その課題をどう解消できそうか。最終的にパナソニック ホームズのリソースをお客さんが見ることになるので、それが他社との差別化になります。どのリソースを使うべきなのかを問い、皆さんにまとめていただき、最終的には一つの解を求めて、それを使う。

山枡: 弊社の強みは、数多くあるハウスメーカーのなかでも歴史があり、大手メーカーでは三番目に古い1963年から事業を行っています。その中でずっとぶれない軸が構造と換気です。そこにプラスして、家電メーカーのグループなので、電化装置やソフトウェアの家への取り込みも強みです。電化製品、ソフトで便利で快適な暮らしを実現するのも、実はそれも構造や換気といった他社にない強みによってよりよく生かすことができます。
もう一つは、数あるハウスメーカーで、まちづくりまで踏み込んでいることです。
相澤: パナソニック ホームズさんの強みは、とてもシンプルなこと。35年という長いローンを考えると、長い目で見た時に、自分たちでメンテナンスすることになるので、意匠性、街並みをバランシングしなければいけません。それが機能的な面でもできているのは、日本のハウスメーカーの中ではパナソニック ホームズのみだと思います。派手好きな人からするとすごく地味に見えるかもしれないけれども、よく見てみれば、外構とのバランスがとてもよい。街並みに直接影響するのが外構で、それが街並みそのものになっていきます。
── それは自ずとお客さまを選ぶということでもありますよね。
相澤: 顧客属性は、パナソニック ホームズの建物なら絶対にずれることはありません。細かいようなことですが、天井の高さ、建具の背の高さの緻密な設計は、定性的に顧客に対してめちゃ効く要素です。柱をどこで抜いて大空間をつくるのか、それは構造に強みがあるから、その大開口がつくれるんだ、ということです。建物のサイズが大きければそれに越したことはないが、南荻窪のような限られたサイズ感でやったとしても、圧迫感はないだろうと思います。意匠は言わずもがなで、よほどのことをしない限り価格から大きくズレることはしないだろうなというのが感覚的に強かった。これは、他のハウスメーカーにはないことです。
街並み、外構、建物設計という検討順番の理由
近藤: まずは街並みという大きな部分からコンセプトにあった計画を検討し、その後、外構・建物設計と詳細を詰めていくことで、街として一貫性を出すためです。街の設計ルールは、統一感が出るように、この物件ならではの、環境に調和をしたものは何かという点から検討します。また建売だけでなく注文住宅も建つ物件となるため、調和がとれた街並みとするため、街並みガイドラインを策定し、一定のルールを設けております。
他の物件での街並み設計では、「この条件を入れるように」と、どちらかというとガチガチに規定を定めるところが多いのですが、この価格帯で制限を多く設けると、お客さまの計画を窮屈にしてしまうケースが考えられたため、ルールで縛りすぎないようにバランスに配慮しています。例えば、門柱ルール、照明の明るさや数などもあくまで推奨とし、制限はしていません。

相澤: ここに住んでいる人は他とは違いそうだねという世界観を出すために、あえてクローズドにして結界をはるか、周辺の街並みに合わせてわざとそこに溶け込むような雰囲気にするかを選択できます。その場合、街としての管理コンテンツを強くしていき、「あの街に暮らす」という憧れとプライドを緻密に設計することもできます。
結果的には街のエントランスに絶妙な感じで結界性を持たせることができました。建物の外構面では重厚感ある意匠でフレームと化粧壁を立ち上げ、プライバシーの確保を大切にしています。実際に、この物件を購入できるような人たちは高所得の方が多い層なので、隔離感を出して世界観を確定させる方がいいという判断です。
まずは街並みを作り、外構を考え、建物は順番としては後に検討しました。一般的には、営業は建物を大きくしたいと思っていますが、それでは外構で何もできなくなる、つまり木を植えられなくなります。街並みをつくろうとするとそれはアウトだからです。その条件下で、設計側は建物をどこまでふくらませるかを検討します。
近藤: お客さまのペルソナに合わせて、ファミリー層は明るめに、DINKS層はシックにと、建物のデザインも少しずつ変えています。
販売方法はまず先に土地を販売してから建物を販売するという順番です。建売が始まってから、実際にお客様を現地にご案内していくという流れで進めます。
設計と営業の対立構造のない環境
相澤: このプロジェクトにおいては、チームの中で設計の人数が多いのが印象的でした。営業が近藤さん含めて2名体制。キングオブ営業の会社の場合、設計が営業に泣かされているイメージしかない世界観の中で(笑)、パナソニック ホームズさんはとてつもなく営業と設計のコミュニケーションがよく、バランスがよい。営業の方が独断専横じゃないのはすごいことです。
設計と営業はどうしても対立構造になりがちで、どちらかというと設計の方がかなりしっかり考えを持っていたりする。すると、営業と軽い論争になることは多々あります。設計から提示されるものの精度が高く、このままいったら良い流れになるだろうなとわかりました。
山枡: 今回、普段の設計と違い高価額帯であるため、設計としても、自分たちが良いと思えるものを、自信をもって提案することができます。営業からするとそれは高い、原価を抑えてくれというのは基本です。こうした答えのない難しい判断がある中で、南荻窪の物件では、「設計」と「営業」だけではない、もう一つの目線がありました。住まわれる方にとって、いかに、良い街並みや、街の価値をつくっていくか。二項対立すると永遠に結論が出ない戦いになるのですが、相澤さんに客観的な意見を言ってもらえる立場で参加してもらったのが大きかったです。
私は本来、営業と設計は意見をぶつけあうべきで、営業がコストを優先しすぎたり、バランスを崩していると思えることがあれば、設計側はブレーキをかけなければいけないと思います。逆に設計が個人の意見を強く主張しすぎることがあれば営業がブレーキかけるべき。こういうふうに折衝して、双方がいきすぎないようにするのが理想的です。今回はその中でも思い切ったことをしながら、双方の合意が取れたのは非常に稀な例かもしれません。相澤さんからメソッドを共有いただき、営業が近藤で、お客様に支持されるというポイントを明確に持っていたからできたことで、営業が彼でなくてはできなかったかもしれません。価格が高くてもここまでつくり上げた価値を訴求していけば、絶対に売れるという自信があります。

近藤: 私は本物件の前に、近隣の南荻窪1丁目の物件も担当していました。販売した時の周辺物件が約1億円で、当社物件は1.2~1.5億円での価格で販売致しました。その根拠として、東京都の地価が上がっていること、当社の建物品質・間取り・設備を考えるときっとお客様のニーズにお応えできると考えました。おかげさまで販売も好調に進捗しております。今回企画している南荻窪二丁目物件は、立地は4駅5路線のマルチアクセスに加え、23区内・中央線沿線・20区画以上の分譲地は11年ぶりの供給という希少性、23区画という大規模分譲で街並みの統一感を出せるという点で他にはない利点が多くあります。インテリアや外構の提案を一つとっても金額に影響します。相澤さんが伴走し、マーケットから設定したターゲット・ペルソナがあったため、それに見合った高価格帯ならではのインテリアや外構を入れることにしました。お客様にお喜びいただける街になると、自信を持って言えます。

結論は同じでも、自分たちで決められるかどうか
── お話を聞いていても、とてもよいムードで仕事が進んでいったことがわかります。
相澤: なればこそ、今回は私が出過ぎないことが大事だと思いました。もともとバランスがよかったので、ここで私が出過ぎると、このチームが「答えを欲しがる人」に変わってしまうかもしれないというのがあった。良くも悪くも、plan-Aがこう言っているからというのが一人歩きしてしまうのがいけないので、いかに自ら納得して答えを出すのかという寄り添い方をしていきました。
近藤: このプロジェクトの始まりは、通常より半年前倒しでやっているので、プランやターゲット設計など、根拠を持って設計思想づくりに進むことができました。相澤さんがいなかったら組めなかったと思います。お客様にも自信を持って理由を示し、ご説明できます。
山枡: 今まではマーケット情報を広告代理店からもらっていたんです。強弱シートを使い、一人ひとりが、上も下も全く関係なく、自分が考えたんだ、ということが今回は決定的に違います。誰かが作った答えがあるのではなく、この敷地を、このターゲットに対して、こう設計しますというのは、みんなで考えた。これが大きいです。
── 伴走の成果ですね。
山枡: これまで、建物、街並みの企画に取り組むにあたってのスタートが遅かったんだなあ、ということがわかりました。ペルソナは全員で決めなきゃ、と思いました。広告代理店が答えをもっているんじゃなくて、設計をして家を建てて販売するのは我々にしかできないことなので。納得してつくって、みんなで売っていくというプロセスの考え方が変わりました。これは社内で展開しなきゃな、と。
近藤: 販売側の目線でいくと、強弱検証から始まるターゲット設定から、プランやインテリアなど全てに至るまで、断片的ではなく全てがつながって企画できたのが大きかったと思います。販売する時にも、お客さまに対して、一つひとつ根拠を持って深堀りして話ができることが自信になりますし、何よりお客さまに喜ばれると思います。
この手法は別のプロジェクトでも展開していきたい。設計プランもよくなり、インテリアにも一貫性が出ることで、結局その思想は販売にもつながっていきます。
山枡: 得られた成果を一つ挙げるとしたら、(外側に)答えを求めてはいけないなと思いました。デザイナーさんから提案を受ける際には、お金を出してオーダーをして、納品物、モノを受け取るようなことがありましたが、そうではなくて、本当に大事なことは、モノでも形でもない、こうやって自分たちで考えて、やるんだ、ということ。これまで伴走という発想が全くなかったので、成長というよりも、それを知れたというところが、私にとってはプラスでした。
近藤: 会社にとってよかったのは、今、山枡が話をしたような企画の根幹の部分ですが、私個人で言えば相澤さんの立ち回りはとても参考になりました。実際に、営業と設計の意見が異なることもゼロではなかったんですが、多分相澤さんは両方を俯瞰して見ていて、もしかしたら8割方営業に寄り添ってくださっているような気がしたのですが、棘のない言い方で、気づいたら然るべき方向に向かっている。これこそ伴走なんだなというのを知ることができました。相澤さんにもきっと考えがあると思いましたが、自分たちで議論して決めていく、その流れを綺麗につくっていってくださったんだなあ、と。
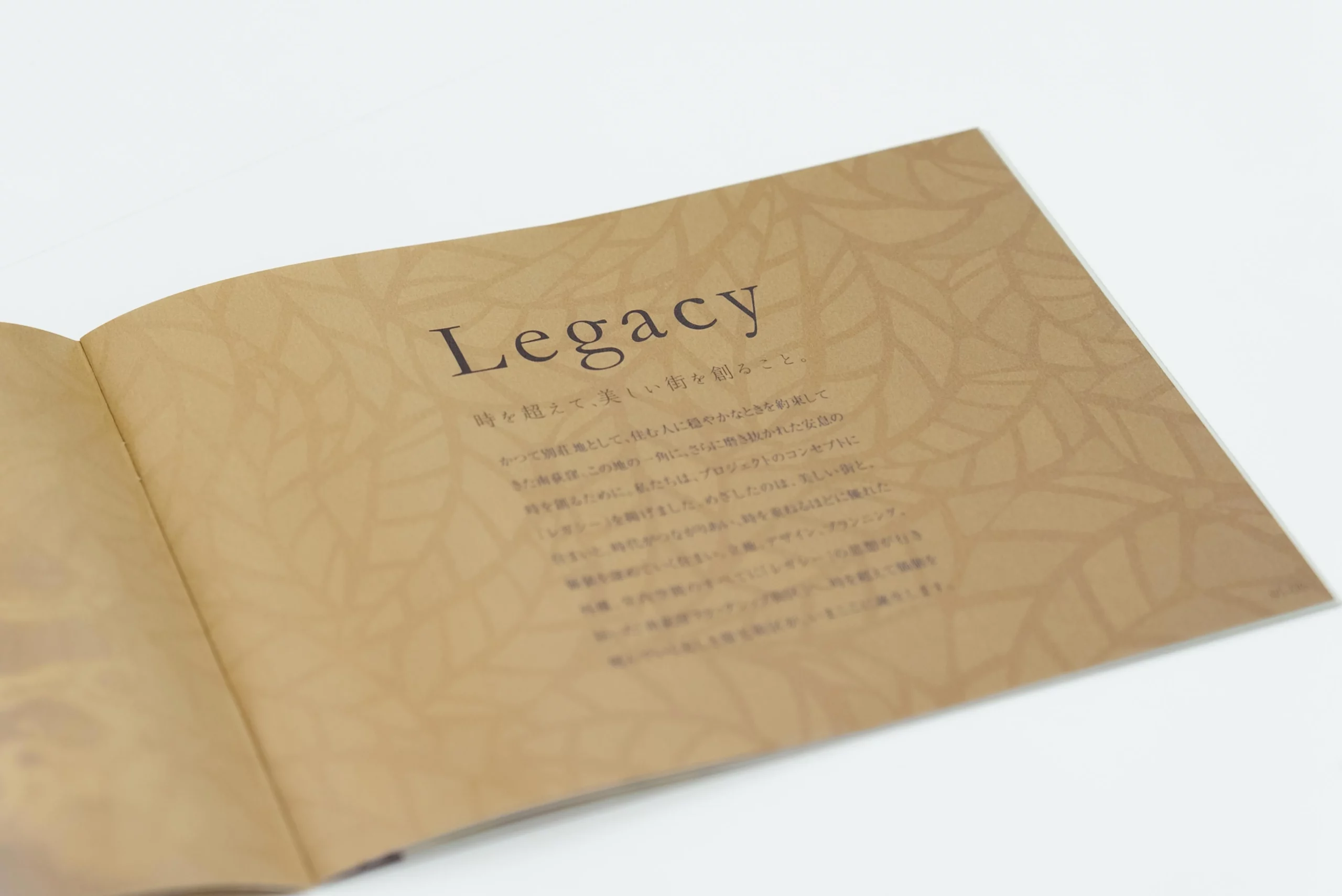
── 最後に、このインタビューシリーズでは、相澤さんを一言で表すなら? とお聞きしています。
山枡: ……いまだにつかめていないですね。仕事の幅も広くて、横浜市、富山県などの仕事もされていて、どういう仕事をされているか聞いたけれど、正直まだわからない。
近藤: 確かに最後までよくわからなかったですね。難しいなあ……あえて言えば、スライムですかね。私が意見をいった時にも、他の誰が意見を言っても、絶対に否定しない。一旦全部スライムのように吸収して、それを大きくして返してくれる。言っていることも合っているけれど、オプションを足すのもその一つですよね。1で持っていった話が、1以上で返ってくる。見た感じはパワー系の印象もあるのですが、やわらかさを兼ね備えていて。スライムで合っているのかわからないですが……。
山枡: それを言ったら、なんか、雲みたいな……背中を押されているけれど、感触がない。
近藤: わかるなあ。
山枡: だけど、風が起きている感じがする。よく見えないけれど。そして、確実に何かが残っているんですよね。
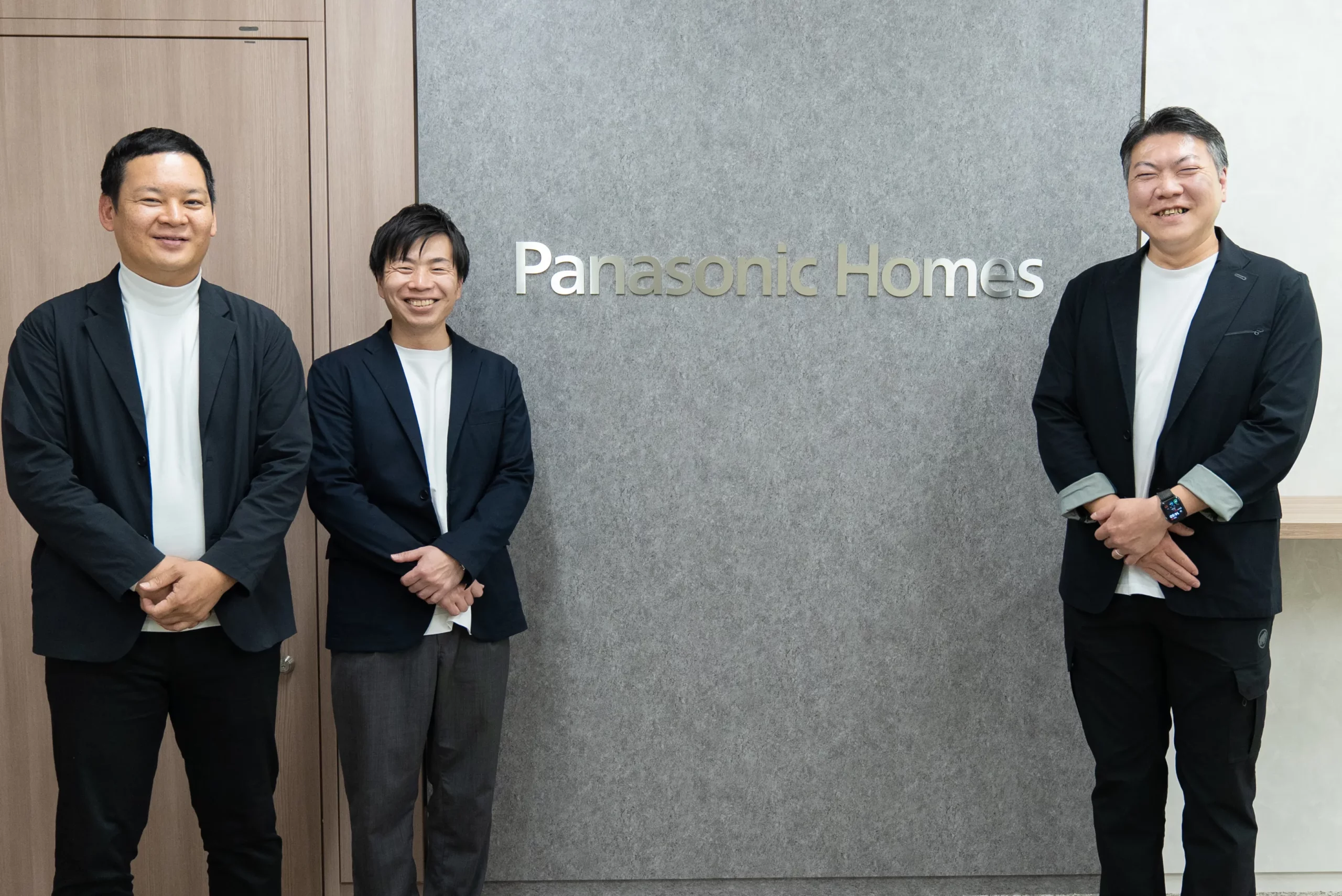
※1 プロジェクト発足当時の部署・役職
Information
パークナードテラス南荻窪 景邸
https://homes.panasonic.com/kyoten/city/minamiogikubo2/
パナソニック ホームズ株式会社
https://homes.panasonic.com/
インタビュー・文=北原まどか
写真=堀篭宏幸

